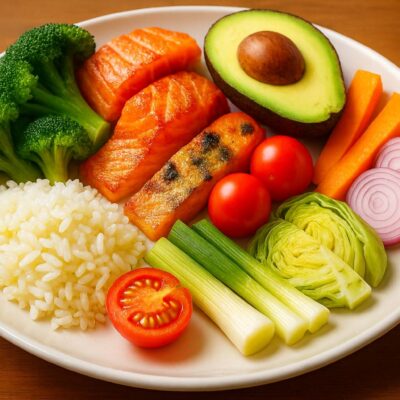食事療法の目的
当院では、食事療法を単なる栄養補充や食材の選択ではなく、根本的な健康改善の手段として位置づけています。腸管免疫や栄養状態、遺伝的要因、環境要因を考慮しながら、個々の患者様の状態に最適な食事指導を行います。
多くの不調(ブレインフォグ、慢性疲労、自己免疫疾患、炎症性腸疾患など)は、腸内環境の乱れや免疫の異常と関連しています。そのため、特定の栄養素を補うだけでなく、なぜその不調が起こっているのかを探り、食事を通じてその原因を調整することが重要です。
アプローチの順序
食事療法は、単に「〇〇を避ける」ものではなく、体の状態を理解し、適切な栄養とバランスを見極めるプロセスです。以下のようなステップで進めます。
- 腸管と免疫の評価
- 腸管と免疫を異常にした原因因子を精査
- 個別の食事プランの設計
- 特定の病態や体質に応じた栄養アプローチ
「〇〇を食べてはいけない」とか「これさえ摂れば治る」という単純なルールではなく、どのように食べれば健康を取り戻せるかを重視します。食事制限が必要な場合でも、栄養バランスを損なわないように調整し、無理なく続けられる形で提案します。
そのため、初診時には詳細な評価を行い、患者様の状態に応じた具体的な食事指導を行います。特定の疾患や不調がある場合には、それぞれに適した方法を柔軟に適用しながら、長期的に健康を支える食事プランを構築していきます。
1. 基本方針
- 個別対応:食事療法は万人に同じものが適応できるわけではなく、患者様の遺伝子、腸内環境、生活習慣を考慮して最適な食事を提案します。
- 腸内環境の最適化:腸内細菌のバランスを整え、リーキーガットやDysbiosis(腸内細菌の異常)を防ぐことが健康維持の鍵となります。
リーキーガットを治すというのは食事法の究極の目標です。下記の各項目は最終的にはリーキーガットを治すことになります。腸から体に良い栄養だけを取り込むはずのゲートが壊れた状態をリーキーガットといいます。
dysbiosis(ディスバイオーシス)の改善は食事法の究極の目的です。食べ方次第で腸内に元々共生している細菌のバランスが変わります。ディスバイオーシスというのは腸内細菌のアンバランスな状態を指します。腸に直接届く食事が大きく影響を及ぼしています。 - 解毒と免疫:腸は食べ物を受け止めるだけでなく、解毒の臓器でもあり、免疫も司ります。腸の重要な作用を担保するために食事法が要になります。
2. 具体的な食事療法の例
アレルギー・腸管免疫に配慮した食事治療の例
- 遅延型アレルギー(IgG型)を引き起こす食品を特定します。
- 腸管粘膜を傷害し、腸管免疫を損ねる食材を特定します。(IgA型の反応。自己免疫に関連)
- 発酵食品、プレバイオティクスを活用し、腸内フローラの最適化をします。
- 花粉症やアナフィラキシーは即時型反応という異なるメカニズムのアレルギーです。アレルギーや免疫が関与する食事の反応は即時型反応だけではありません。食事療法を検討する際は、広い視野でその患者様に関与しうる食事の反応を全て見直します。
- 化学物質過敏症や電磁波過敏症も、対象となる化学物質や電磁波のみをひたすら避けるのではなく、同時に腸内環境を整え、隠れた食物アレルギーの有無の確認も重要です。
レクチンに配慮した食事法の例
- レクチンの不適合は腸内環境、腸管粘膜におけるWGA抗体の有無、リーキーガットの検査などで判別します。
- レクチンは植物由来のタンパク質で、腸管の透過性を高め、リーキーガットの原因となるものです。
- レクチンの例: 小麦その他の雑穀(白米以外ほとんどがレクチンを含む)、ナス科(トマト、ナス)、ほとんどの豆。
がん補完療法における栄養・食事療法の例
- 一般的な癌に良いとされる食品やサプリメントを闇雲に勧めるのではなく、遺伝子発現に基づいた最適な栄養素を選択します。
- 抗炎症食の実践、食事由来の環境要因(発がん物質)も避けます。
- 慢性感染症(例えばライム病)の治療との統合的アプローチ。ライム病は慢性感染の中でも癌の進行や再発に寄与するためです。この際はライム病に適した食事法を配慮した上でメニューを組みます。
- 癌リスクの高い方や癌の治療中の方の栄養療法は遺伝子発現の検査に基づくニュートリジェノミクスのデータを活用したり、RGCC社の感受性検査を参考にして個別対応をします。
SIBO 小腸細菌異常増殖症のための食事法の例
- 「FODMAP食を減らすこと」(fodmapとは発酵しやすい炭水化物など)はもちろんですが、SIBOの原因因子をできる限り早く見つけ出すことが鍵になります。SIBOの本当の原因がFODMAPではなく、他の食材であったり、他の病気であることがあるからです。
- 抗菌・抗真菌対策をすることもあります。イーストコネクションの食事法を参照してください。
イーストコネクションのための食事法(真菌、カビ、酵母、カンジダ関連)
- 体内のカビの増殖を抑えるための食事法・栄養法です。消化管カンジダ症、カンジダ以外のカビの菌が体内に感染している方、環境のカビを取り込んだ方が対象になります。
解毒のための食事法の例
- 水や食材からも重金属、有機溶剤、残留農薬や抗生物質などさまざまな物質が含まれるので、この対策についての食事法を含みます。
- 個別対応は各患者様の毒の種類と蓄積度に適したアドバイスを行います。
骨の健康のための食事法の例
- アルカリ化:酢(リンゴ酢など)、ミネラル補給
- 腸内環境の調整:酪酸産生菌を増やし、ビタミンKを腸内で合成させましょう。
- ビタミンD3と昼間の外出
- 骨はカルシウムを摂れば良いというわけではありません。35歳以上の方はカルシウムを吸収できなくなるので個別対応で骨対策をします。
MCASのための食事法の例
- ヒスタミンを多く含む食品(発酵食品、熟成肉、加工品、アルコールなど)を減らす方法です。MCASの疑いのある方が実践する特殊な方法です。
- MCASの原因疾患を評価し、根本治療とともに食事を調整します。詳しくはMCASのページを参照ください。
脳とメンタルの健康のための食事法の例
- 腸脳相関の視点から、リーキーガットを防ぎ、脳への毒素流入を防ぐ必要があります。
- 腸に何か悪いことが起こっていたら脳が健康ということはあり得ません。つまり、食べ物が間違っていたり、食事法次第では脳の健康が左右されるということです。
- 例えば腸にはセロトニンの受容体があります。
- うつ症状、不安、不眠、イラつき、ADHD、自閉症、慢性頭痛、物忘れ、ブレインフォグ、これらの悩みは精神・神経科だけに限定せず、食事療法に目を向けることはとても重要です。
ホルモンバランスのための食事や栄養療法の例
- 甲状腺機能を最適にする食事法(亢進、低下、自己免疫)
- 性ホルモン(女性ホルモン・男性ホルモン)のバランスを最適にする食事法
- 副腎疲労をサポートする食事法
- メラトニンをサポートする食事法
- 内分泌撹乱物質(ビスフェノール、フタル酸エステル、フッ素化合物などの有機化合物や水銀、鉛など)の回避のアドバイス。
- ホルモンについては転換酵素や受容体についての配慮も含みます。
代謝の問題のための食事法の例
- るいそう・サルコペニア、ホルモン系、肥満、メタボに対応します。
- 血糖、血圧管理、高脂血症のための食事療法も行います。
- ケトジェニック食事法など。
アンチエイジングの食事・疲れやすい人のための食事
アンチエイジングの食事法は多くの方が興味を持つテーマです。近年の研究では、老化を抑制するためには cellular senescence(細胞老化)の抑制 が鍵となることが示されています。ポリフェノールは老化の主要なメカニズム(酸化ストレス・慢性炎症・DNA損傷など)に対して有効であり、遺伝子発現やエピジェネティクスにも影響を与えることが分かっています。
しかし、本当に若さを追求するのであれば、レスベラトロールやケルセチンなどの ポリフェノールのサプリを飲んだり、フラボノイドが多い果物や野菜を食べるだけでは限界 があります。
ミトコンドリアを若く保つために カロリー制限 が効果的であることも研究で知られています。細胞老化もミトコンドリアの老化も、老化のメカニズムの基本です。また、免疫老化 と 慢性炎症 も関与します。免疫を老化させないための食事法には、免疫を酷使しないこと や 免疫細胞が並ぶ粘膜を健康に保つこと などの配慮が必要です。慢性炎症の対策としては、まず 炎症の元を取り除くこと から始めます。ご自身が気づいていない炎症の元は意外と隠れています。
アンチエイジングの食事法は、単にビタミンを摂るという単純なものではありません。慢性炎症、ミトコンドリアの老化、幹細胞の量と質の低下、免疫老化、テロメア短縮、エピジェネティック遺伝子の変化、細胞老化、オートファジーの低下(解毒能力の低下)、マイクロバイオームのアンバランス 、同化ホルモンと異化ホルモンの逆転などの老化メカニズムを理解し、それぞれに対応することが重要です。
最初ある程度のストイックさは必要になるかもしれませんが、一度下地づくりができれば、簡単なメンテナンスによって外見の若さ、内臓の若さ、生き生きしたエネルギー を維持できるようになります。
ご興味がある方は当院にご相談ください。
3. 個別対応の食事療法
食事療法は画一的なものではなく、各患者様の疾患はもとより、遺伝的要因、腸内環境、環境要因、心理的な因子、住居や毒素暴露などの影響を考慮し、ニュートリジェノミクス、オルソモレキュラーと機能性治療の手法の視点から最適化します。
食事は単なる栄養補給ではなく、身体を治癒へ導く重要な要素です。当院では、患者様一人ひとりに合わせた食事療法を提案し、根本からの健康改善を目指します。