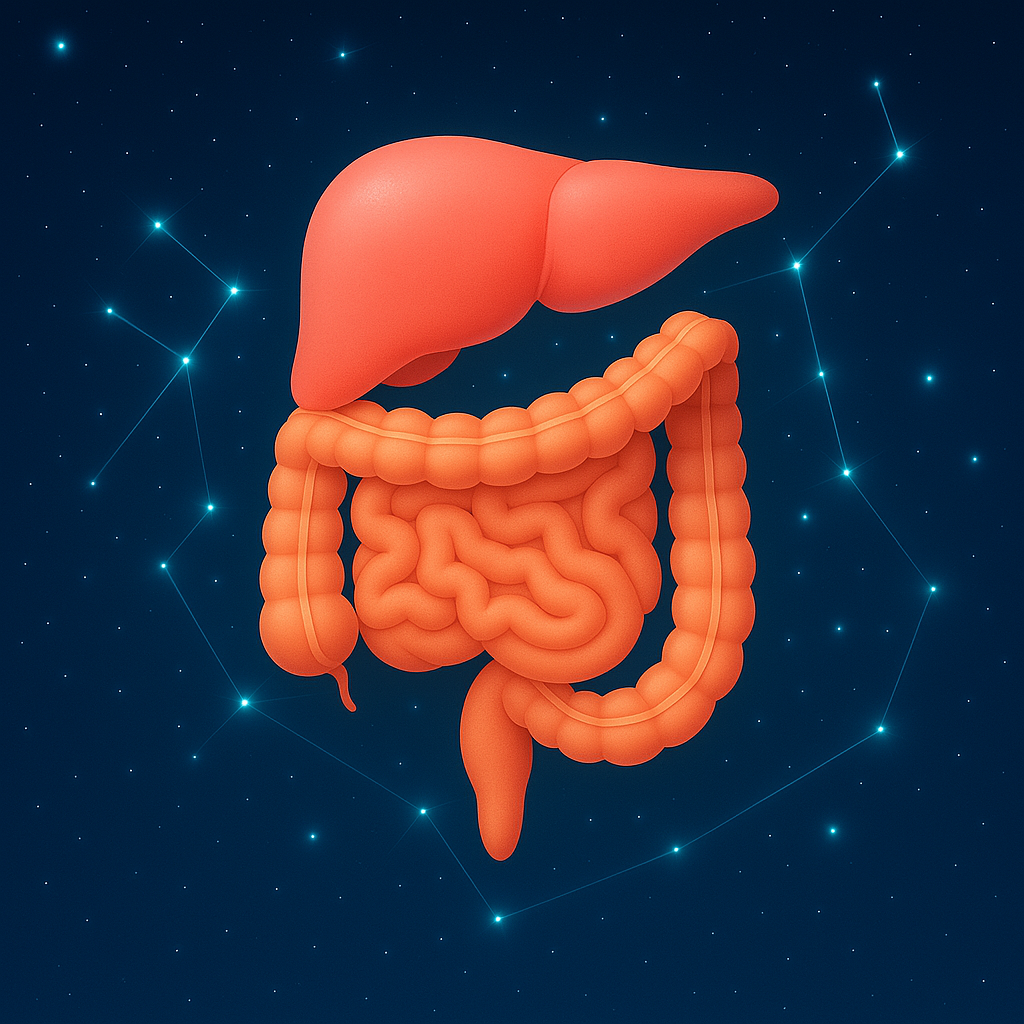
近年、肝臓の病気として注目されている「非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)」。(発音はナッフルド、ちょっと可愛らしい) アルコールをあまり飲まないのに肝炎や脂肪肝を発症するという病気です。
健康診断で肝機能の数値の軽い異常を指摘されたことのある方、放置していませんか。肝臓には痛みを感じる神経がないので、病気になっても自覚症状があまりありません。黄疸がないし、特段困っていることもなし、飲酒なし、太ってない、薬もほとんど飲んでいない、肝炎ウイルスにはかかっていない、など肝臓の数値が悪くなる理由が特にない方、かたや医者には規則正しい生活してください、翌年まで様子見、などと言われたりします。危機感を覚えにくいですね。
痛くないがゆえに肝臓は沈黙の臓器と言われます。しかし、静かにナッフルドは世間に浸透し、着実に増えています。
では今日なぜNAFLDが増えているのでしょう? その鍵は肝臓と腸との関係、文字通り「腸肝相関」です。腸内細菌叢のアンバランス、ディスバイオーシスという状態は、肝臓の健康に大きな影響を与えます。腸の問題が大きくなっているので、肝臓に影響が及んでいるのです。
2023年のPabstの論文では、腸と肝臓が物理的・免疫的・代謝的バリアを通じて密接に連携していることを示しています。これらのバリアは腸内の有害物質、食事由来の成分、微生物の老廃物や毒素から肝臓を守ってくれており、健康な状態では腸肝軸の恒常性(ホメオスタシス)を保っています。
ところが腸内細菌叢のアンバランスが起こった場合、腸肝相関が崩れ流きっかけになり、肝臓の障害へとつながることがあるのです。
ナッフルドNAFLDとは?
NAFLD(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease)は、アルコールの過剰摂取とは関係なく、肝臓に脂肪が蓄積する病気です。
ナッフルドが進行すると「非アルコール性脂肪肝炎(NASH)」に発展し、肝硬変や肝がんのリスクが高まります。そのため、ナッフルドの段階で早期に対策をします。
食生活の変化、運動不足、ストレス、腸内環境の悪化などが原因となり、インスリン抵抗性(血糖値を調整するホルモンの働きが悪くなること)を伴って進行することがあります。全身の代謝疾患と肝臓が関与するので、昨年からはナッフルドがマッスルドに名称変更する動きもあります。マッスルド(MASLD: 代謝機能障害脂肪性肝疾患)
腸と肝臓の密な関係
ここからは腸と肝臓の「腸肝相関(gut–liver axis)」と呼ばれる密接なつながりについて、実際どのようにしてつながっているかみていきましょう。
類似の用語に「腸脳相関」があります。腸と脳のがつながっていることはよく知られるようになりました。一旦おさらいのために脱線します。
まず…
●腸は第2の脳です。
●腸の問題は脳に反映されます。
●腸に問題がある以上、脳は健康になり得ません。
では、肝臓に戻りましょう。腸脳相関ほど周知されていない、「腸と肝臓の関係」ではありますが、近年は多くの研究者や治療かから注目されています。腸と肝臓は物理的に近く、直感的にわかりやすいはずです。端的に言うと、腸内環境が悪化すると、肝臓に悪影響を及ぼします。逆も然りです。腸内の毒素(毒ガスも含みます。)は門脈という太い静脈を通って肝臓に到達し、肝臓にダメージを与えます。腸の問題は、直結する太いパイプがあるため、肝臓に反映されてしまうのです。
つまり…
●腸に問題があると肝臓に反映されます。
腸で吸収された栄養素や水分、代謝産物、そして毒素に至るまで、すべてがまず最初に門脈という太い静脈を通って肝臓に届けられます。
門脈は、腸と肝臓をつなぐ物流ルートです。肝臓はいわば腸から出荷された荷物が最初に集まる仕分けセンターです。
荷物を仕分けし、ゴミもついでに分解廃棄する機能を持つのが肝臓です。たとえ門脈に、腐った荷物(毒素や細菌のカス)が紛れ込んでいてもちゃんと分解します。黙々と地味に分解と廃棄をし続けます。
門脈の大渋滞が起こると?
本来、肝臓はそうした異物を見分けて分解・解毒する体内最大の分解処理工場です。肝臓は解毒の臓器として有名ですね。でも、あまりにも荷物が多すぎると何が起こります…?
肝臓はフル稼働モードに突入し、過労状態になります。
渋滞した門脈では、毒素が肝臓に入る手前で立ち往生し、渋滞度合いによってはむしろ腸に負担がかかることがあります。その結果、全身の炎症反応や免低下、慢性疲労や脳の不調につながります。
ちなみに肝臓は分解とか廃棄だけの単純スクラップ工場ではなく、しっかりガードマンを備えています。肝臓特有の免疫担当細胞のことで、クッパー細胞という名前を持つガードマンです。クッパー細胞が肝臓に流入してくる異物や有害物質に反応して作動し炎症反応を起こします。
腸由来の過剰なゴミのせいで肝臓に負担がかかりすぎ、肝臓内の免疫細胞も過剰に反応し、肝臓の炎症がおこり、さらに、進行すると体全体の不調に発展しうるのが腸肝相関の注目点です。
腸内細菌は、肝臓の運命を決定します。
1.腸のディスバイオーシスと肝臓
最近の研究では、腸内細菌の作り出す物質が肝臓に届いて炎症を引き起こすことが指摘されています。腸内細菌叢のアンバランスを起こす因子は肝臓を直撃します。肝臓を直撃するものとはアルコールだけとは限らないのです。
- 一部の腸内の悪玉菌は、リポポリサッカライド、LPSという炎症性物質を作ります。そしてその害悪なLPSを腸内にまき散らします。LPSは腸の粘膜を貫通する能力があるので、リーキーガットの有無にかかわらず、全身に炎症を拡散する物質です。
- 腸内細菌のバランスを崩す原因には、遅延型食事アレルギーやセリアック病などの食材由来も多いです。特定の食物を消化できないとき、腸には未消化の食材が残ってしまいます。未消化の食物とは生ごみです。それは腐敗して腸内環境を乱します。
- 上記のような腐敗ガスや腸に発生した毒素などは門脈ルートに乗って、近所の肝臓にヒョイっと到達します。
- 肝臓の免疫細胞が過剰に反応し、炎症や線維化につながります。肝臓の繊維化とは、肝臓が石のようにゴツゴツ硬くなってしまう最終形、肝硬変のことを指します。肝硬変はお酒の飲み過ぎや肝炎ウイルスだけが原因とは限らず、腸の悪玉菌も関与しているのでした。
- 腸内環境の乱れは肝臓の病気の火種になりえます。
- 腸管バリアの破綻があれば、腸内の毒素は肝臓に悪影響を与えやすくなります。
- SIBOの方、過敏性腸症候群、お腹が張って苦しい、便秘、下痢、原因不明腹痛、ピロリ菌にかかったことのある方、肝臓に負担をかけているかもしれません。肝臓はかなり悪くなるまで、耐えて耐えて沈黙したままなのです。
2. カビ・カンジダの異常増殖
腸内細菌のバランスを崩す要因として決して外せない、問題の大きさとして最大とも言える、「カビ」があります。環境カビへの暴露が続いた時、カビ毒の炎症が強いので、腸のディスバイオーシスとリーキーガットを促進します。カビ毒(マイコトキシン)は腸から肝臓へ運ばれ、解毒機能をフル回転させ、肝臓内にはマイコトキシンが充満し、肝臓はオーバーヒートします。カビの種類は多いので、ざっくり2種類例に挙げます。
例1 カンジダ(Candida):腸内の真菌バランスを崩す“酵母菌”
- カンジダ菌はもともと人間の体内に存在する常在菌の一つですが、特定の薬を飲みすぎたり、免疫が弱ったり糖分過多の食事が続くと、異常増殖して病的な感染量になります。
- カンジダ菌の代謝産物、アセトアルデヒドやアラビノースなどの有機化合物が肝臓に負担をかけます。
- カンジダ菌自体もカンジダ菌が産生するカビ毒も腸粘膜を傷つけ、リーキーガットのリスクを高めます。
例2 アスペルギルス(Aspergillus)が産生するカビ毒(マイコトキシン)、オクラトキシンなど
室内の高湿度や結露から繁殖したカビが産生するカビ毒は肝機能のダメージを起こします。
- アフラトキシンやグリオトキシン、オクラトキシンは肝毒性が強く、ナッフルドを発症させます。
- 解毒に必要なグルタチオンを大量に消耗してしまいます。
3. ピロリ菌と腸管免疫の攪乱
ピロリ菌は胃に感染する細菌ですが、消化管全体の免疫環境に影響を及ぼし、ディスバイオーシスを促進します。ピロリ菌は人間の胃に住みつきながら胃酸を中和しながら自分が生存しやすい環境を整えるのが特徴です。加えて、制酸剤(胃酸を抑える薬、ガスターやタケプロンなど)の長期過剰服用をすると胃酸を減らしますので食べ物を消化する力が衰えます。ですから、ピロリ菌にかかっていたり、制酸剤を飲みすぎていると、食べ物を消化しにくくなり未消化の食品が胃腸に残りやすくなります。腸内細菌の過剰増殖(SIBO)のリスクを高め… もう想像がつきますね。ピロリ菌も腸肝相関に悪影響を及ぼします。
そもそもピロリ菌感染は胃炎発症や胃がん発症のリスクを高めます。また、感染部位の胃以外、全身機能に影響を及ぼしうる因子として知られています。ピロリ菌と高血圧、ピロリ菌と肌荒れや酒さ、ピロリ菌と糖尿病、ピロリ菌と脂肪肝、ピロリ菌と貧血、ピロリ菌と心臓病、ピロリ菌と自己免疫疾患、ピロリ菌と不眠症などです。
4. ライム病の肝臓への影響
え、ライム病お前もか? と言ってしまいそうになりましたか。(ライム病はダニ媒介による感染症です。ライム病を聞き慣れない方は詳細を割愛しますので他の記事を参考にしてください。)慢性ライム病とその複合感染の感染症(バベシアやバルトネラなど)は、肝臓に多大な影響を与えます。ディスバイオーシスやリーキーガット、胆汁うっ滞を引き起こし、肝臓への毒素流入を増やします。特にバベシアはヘム代謝異常を通じてビリルビンの破壊が起こるので肝機能に負荷をかけます。バルトネラの主症状の一つに肝血管腫が含まれます。ライム病の治療中の方は思い当たる節があるかもしれません。治療経過に伴い、肝機能の数値のアップダウンが見られます。
最後に・・・
腸肝相関(gut–liver axis)は、腸と肝臓が連携して全身の恒常性を保つ高度なシステムです。その連携のとれたバリア機能が崩れる背後には、食事由来、毒素、腸内細菌のアンバランス、カビ毒、ピロリ菌感染、ライム病などをはじめとする多くの因子がかくれています。
肝臓の健康は意識したくても分かりにくく、症状だけで気づくには劇症肝炎、肝硬変、肝臓がんまで進行するのを待つことになるでしょう。健康診断の肝機能の異常数値や超音波検査で脂肪肝を指摘されたらチャンスです。同じ検査を短期間に何度受け直しても変わらないでしょう。
もしや自分の体の分解廃棄解毒工場は作動できないんじゃないかしら、と肝臓に思いを馳せてみてください。当院ではもちろん全身機能を大局的に捉えながら、腸肝相関のパズルのピースをはめ、最適健康を目指すお手伝いをしております。
参考文献
Kiseleva YV, Maslennikov RV, Gadzhiakhmedova AN, Zharikova TS, Kalinin DV, Zharikov YO. Clostridioides difficile infection in patients with nonalcoholic fatty liver disease-current status. World J Hepatol. 2023 Feb 27;15(2):208-215.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10011916
https://doi.org/10.4254/wjh.v15.i2.208
偽膜性大腸炎を起こす腸内のクロストリジウム・ディフィシル菌と脂肪肝の関係についての論文です。腸内環境と腸粘膜の状態が肝機能に影響を及ぼすという内容です。ディスバイオーシスとNAFLDに着眼しています。
Kraft S, Buchenauer L, Polte T. Mold, Mycotoxins and a Dysregulated Immune System: A Combination of Concern? Int J Mol Sci. 2021 Nov 12;22(22):12269.
https://doi.org/10.3390/ijms222212269
カビ菌への暴露とその毒素(マイコトキシン)の全身への作用を各臓器、組織、機能、後遺症について議論した論文。腸肝相関、腸脳相関、胃腸障害、過敏性腸症候群、ディスバイオーシス、認知機能、免疫系の悪化、慢性炎症なども包括的にカバーしています。
Pabst, O., Hornef, M.W., Schaap, F.G. et al. Gut–liver axis: barriers and functional circuits.Nat Rev Gastroenterol Hepatol 20, 447–461 (2023).
https://doi.org/10.1038/s41575-023-00771-6
肝臓と腸の密接な関係について、両者は常に情報交換’’cross talk’’をしていることをレビューした文献。



